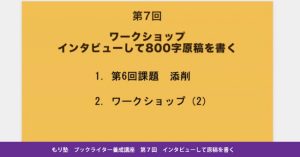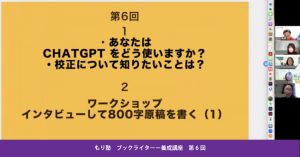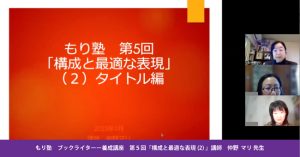専業主婦から出版界で活躍するライター、編集者へ! 森恵子の再就職奮闘記「ハウスワイフはライター志望」第21回。
トンデモナイ対談を、見事まとめあげたことで、次々仕事が舞い込むことに。そして、今度やってきたのは女性雑誌掲載の「広告タイアップ記事」。
「広告タイアップ記事」という仕事
1989年。前年末、あの対談をまとめた編集プロダクションから、次々仕事がやってきた。女性雑誌掲載の「広告タイアップ」の連載というものもやってきた。
広告タイアップは記事体広告、あるいはペイドパブリシティ(略してパブ記事)とも呼ばれるらしい。編集記事と純広告のハーフ的存在だ。
タイアップには、ひとつの記事にひとつのメーカー、あるいはひとつの商品しか登場しない。でも、インタビューや対談の形態をしていることが多く、それなりに読めるから編集記事と区別がつかない雑誌読者も多いはず。それが広告タイアップだ。
連載のほかに、単発のタイアップの仕事も入る。1年間の連載が終われば、また次の連載。
うれしいことだけど、ストレスも多かった。
クライアント(広告主)
⇩
広告代理店
出版社編集部
⇩
編集プロダクション
⇩
私
そんな経路で私のところに、指示が届く。
私はまぎれもなく、末端労慟者。
末端労働者の困惑は、記事を書いたあとで記事内容にそぐわないタイトルが、雲の上から降ってきたりすること。
そんなとき、末端労慟者のよくものを言う口がどれだけ動いても、雲の上までは届かないしくみになっていること。
末端労働者の名前も明記されるが、書き替えを趣味とする人がいるらしく、木に竹をついだような無断書き替えが多いこと。
その書き替えはクライアントの要請と関係のない部分にもあること。
ああ、それに書き替えた文章が私のものより良くなったと、とても思えないことが悔しかった。
「書き替えるなら名前を消していただけませんでしょうか」と言えない自分が腹だたしかった。
書き替えられない文章を書こうという末端労働者の努力などとは関係なく、ついにはそれを趣味とする人がいるのだ、という結論に落ち着いたのは、ずいぶん後のことだった。
もちろん「良い」ときは「良い」と言い、手直しが必要なときはお互いの納得がいくまで電話で話し合うという仕事もあったが。
そんなわけで末端労働者はある系列の広告タイアップの仕事にかかると、自分の位置と文章力のなさを呪い、夜更けの風呂の中で「チクショー」とつぶやいたり、丈夫な胃がシクシク、キリキリ痛んだりした。
電話から響いた柔らかな大阪弁
そんなある夜、電話が鳴った。
「森さんですか。まぁ、ごぶさたしてます。お琴の小泉です。元気でいてはる?」
柔らかい大阪弁が受話器の向こうから響いた。
小泉先生とのご縁は、10年ほど前にたった半年。3月に教師を辞め、10月に結婚するまで花嫁修業と称して「文章」と「琴」を習いにカルチャーセンターヘ通った。「文章教室」は多田道太郎先生。そして「筝曲」が小泉栄子(現・小泉玲紫)先生だった。
専業主婦になる前の期限つきの自由時間に、せめて好きな文章とあこがれの琴にふれておきたかった。
琴のお稽古を始めるとすぐ、私の不器用さが身にしみた。予想通りのことだ。
でも楽しみをほかに見つけた。
大和楽の名取でもある小泉先生の声に聞きほれること。先生が弾く入門曲をうっとり聞くこと。
それに先生は美しかった。真っ白なすべすべした肌に、特別大きな瞳。大きな宝石がよく似合うゆったりとした雰囲気。
小泉先生には「花」があった。
それは「生田流筝曲」という伝統芸能に、あふれる情感を加えて「小泉さんのお琴」へ昇華させている人が持つ「花」のように、私には思えた。
その半年は、先生の間近でうっとりとお琴を聞くために唄を聞くために、そして叱られるために通ったようなものだ。
でも、たった半年の劣等生の私になぜ?
電話の声は続いた。
「お子さん、幾つにならはった?今、何してはる?」
子どもたちが8歳と5歳になったこと。4年前、専業主婦からフリーのライターになったことを言った。
「そう……。そう……。それはええことやわ。あんた、書けるお人やから」
「とんでもありません!」
私の返事は悲鳴に似ていた。そんな声など聞こえなかったかのように先生は続ける。
「あんたが、あのカルチャーセンターの小さな雑誌に書いてはったでしょ。私のこと……。あれが印象に残ってますのんや」
うれしい。でも、恥ずかしい。
「私ねぇ、去年、糖尿から目ぇが見えへんようになったんよ。そやけど7回手術して、今は眼鏡かけたらボーッと見えるようになりました」
まぁ、と言いかけた私の声に重ねるように先生は続ける。だから会いたい人には会っておきたい。
この木曜から土曜まで、演奏会のために上京するから会えないか、と。
好きやないとでけへん。好きやったら、できる
金曜日、先生に会いに出掛けた。ホテルのフロントから先生の部屋に電話した。
エレベーターの前のソファに座って先生を待った。
長い無沙汰のあと、久しぶりに知人に会うときの心のざわつきを感じながら——。
どんなふうにお会いすればいいのか、わからなかった。
エレベーターの扉が、何度も開いたり閉じたりした。
何度目か扉が開き、また男たちのグループが降りてきた。
それを眺め、扉から目を離したほんの少しのあいだに、小泉先生は私のほうへゆっくり近づいていた。
心もとない歩みだった。
立ち上がったのに駆けよりもせず、私はじっと先生を見ていた。
「10年前と、いっこも変わらへん。変わらへんわ」
先生が私に近づきながら、そう言った。
「先生もお変わりなく」
そう言いたかったのに言えず、私はただつっ立っていた。
先生の大きな瞳は、ぶ厚いレンズの奥でゆがんでいた。
二人でそろそろ歩いて、近くのラウンジに腰をおろした。
話し始めても、私の気持ちはまだどこかでぎくしゃくしてしていた。
10分、20分——。
先生と私が互いに近況報告を終えたあと、私はこんなことを口にしていた。友人にも夫にさえ、言えずにいたことを。
「前はすらすら書いてたんです。でも、このごろ、なかなか書けません。自分の文章がすごい下手なんじゃないか、と思い始めて。雑誌に載った自分の文章なんか、見るのもイヤです」
「どこがいけないか、自分でもわかってるつもりです。客観的に書くっていうのが足りないんじゃないか、そう思ってます。だから、インタビューした人を素敵だと思えば思うほど、むずかしくて」
ひとつひとつの言葉に先生はうなずいた。
「作曲も同じことなんよ。ええ旋律が浮かんだからというて、それだけつなげてもあかんの。主張の強いメロディーばっかり並んでてごらん。聞くほうは何が何やらわかりません。それにしんどうなる。作曲も文章書くのも、似てるねぇ。そやけど、あんたはもうそのことに気ィついたんやから、いずれそれができます」
「そう信じようと思ってます。でないと、やっていけませんから……。下手の横好きでも好きなんです。文章、書いてるのが……」
「下手の横好きなんてあらへん。人間、『好き』という二文字に始まって『好き』という二文字に終わりますのんや。好きやないとでけへん。好きやったら、できる」
センセ、おおきに。
私、がんばってみます。
タイアップの仕事も、続けてみます。
とうとう、やったね!
その後も広告タイアップのストレスは続いた。
書き替えられない記事を書きたい。私はそれだけを思い続けた。
出版社の担当者に初めて会ったのは、ふたつめの連載が始まって、しばらくしてからだった。
「あなたがこのシリーズを書いてくださってるんですか。編集長もとてもいい記事だと喜んでました」
私の記事が「いい記事」であるためには、編集プロダクションの企画や、シリーズに登場するレギュラーの人柄がかなりのウエイトを占めている。
でも、私は自分をねぎらった。
「続けてよかったね。とうとう、やったね」
(次回に続く)
もっと自分自身を発揮できる仕事がしたい! 仕事のやり甲斐を求めて出版社へ営業に行き、ついには自分の企画でシリーズを始めることに! そして仕事は深夜まで……。
Vol.22:「夜、外でどんなお仕事をするの?」は、2024年2月公開予定です。
これまでの話はこちらのサイトで読めます↓↓