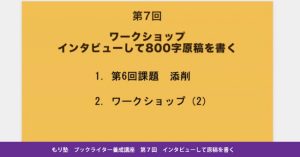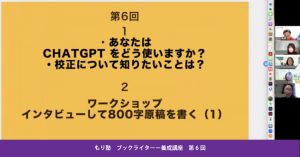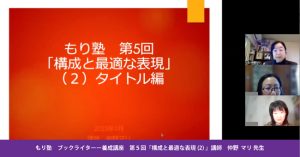専業主婦から出版界で活躍するライター、編集者へ! 森恵子の再就職奮闘記「ハウスワイフはライター志望」第23回。
私はプロのライターで編集者! 実績を積んで、プライドを持って仕事してるのだけれど、世の中からはそういうふうには見られていない?——時にはムカっとすることも。
粋なきもの姿=オトコを誘うためのもの??
「あんた、このタンスの中のきもの、どうするの」
母が上京すると、うるさい。
しつけのついたきものをタンスからとりだしては、ため息をつく。
「きもの雑誌の仕事してるんやから、たまには着なさい」
ハイ ハイ。
きもの関係ではないけど、仕事先で肩の凝らないパーティーがあるから。
私たちは、白い倫子地に黄や赤や緑の小さな水玉を絞った小紋を選び出し、
黄緑のちょっと光った帯を合わせる。
母の着付けは私の身体によくなじむ。
昔のまんまだ。
姿見を見る。
パーティーと聞いて、
母は気合いを入れすぎたようだ。
姿見には、ちょいと粋な私がいた。
パーティーに出向く。
私より少し若い男性編集者が、
きもの姿の私を見て言う。
「よく似合いますねぇ。チイママみたい。
でも半端な店じゃないョ。銀座のかなり大きい店のチイママ」
「ありがとう。
じゃあ、テイシュが死んだら、しがないライター稼業はやめて、商売替えすることにするわ」
「うん、イケル。絶対イケル」
が、私がこのパーティーでチイママもどきをやるハメになるとは思いもしなかった。
中年男性のゲストたち数人が私のまわりに群がる。
名刺交換が始まる。
「では、あなたには特別な名剌を」と、一人の中年男が純金製の名刺を差し出す。
わぁ、悪趣味。
「一枚、千円くらいするんですよ」
値段なんか聞いてないって。
別の男。
「先日、名刺を差し上げましたから、今日はこれを差し上げましょう」
会社の名入りテレホンカード。
帯の間にその名剌をはさんだら、私はほんとにチイママになってしまいそう。
だから、システム手帳に入れる。
私だって彼らと同じゲストであるということに気づく男は、いないらしい。
私の名刺に書かれた住所を見て、ひとりの男。
「ぼくの隣の駅なんですねぇ。
帰りはご一緒しましょう」
ヤダヨ! べぇ~ダ。
チイママ太鼓判の私は、
その言葉をスルリとかわす。
「セクハラってご存じかしら」とでも言ってやるべきだったかしら。
粋なきもの姿=オトコを誘うためのもの。
彼らの頭にあるのは、そういう図式らしい。
そういう通俗なアタマが揃うパーティーだとはつゆ知らず、白い倫子に粋な着付けとは、
こちらにも落ち度があったのかもしれない
——なぁんて、つい思っちゃうじゃないか。
私は、装う。私のために!
帰りの地下鉄の中で、
「きもの姿は誰のためのものか」という命題(?)について考えてみた。
結論は出ない。
その後、
非論理的な私のアタマは命題を勝手に変更し、
「自分自身のためにきものを着ているということが、ほかの人たちにもわかるようなきものとその着付け、およびシチュエーション」
について考察を巡らす。
こういう現実的な課題なら私にも結論は出る。
その日をゆっくり待とう。
ある日、きもののロケで、カメラマンと険悪なムードになってしまった私は、気分転換にきものを着ることにした。
撮影に間にあわせるために急いできものを染めてくださった老舗に、撮影の済んだきものを返しにあがる日だった。
藍大島のしつけを取った。
胴裏がすっかり黄ばんでいる。
10年以上も、タンスの中で眠っていたのだから。
楽な着付けで、大島を着た。
胸元は詰まりすぎず、開きすぎず、
まずまずの出来だ。
駅前の書店で本を買った。
上野千鶴子さんの「スカートの下の劇場」。
私は自分のために藍大島を着て、
気鋭のフェミニストの評論を読みながら、
仕事に出掛ける。
なんと私らしいアコガレを散りばめた日であることか。
なめたら、いかんぜよ!
電話口で編集者の不機嫌な声がした。
「森さん、『百人一首』の件、こちらで調べたら、
新しいことがいろいろ判明しました。
あの説明は違います。
書き替えてくださいっ!」
ナニィッ!
どこがどう違うってのサ。
ちょいと調べてどんな新事実が判明したのか、言ってもらおうじゃん。
だいたい、アンタが違うって言いたいところは見当ついてるけどサ。
「違うとおっしゃるのは、障子のところでしょう。
障子じゃなく襖だとおっしゃりたいんでしょう!」
私は尊敬語を使って冷たく言い放つ。
20種類近くのゲームの起源をそれぞれ、たった300字にまとめるという、
冷静に考えれば「しょうもない(つまらない)」仕事でアタシたちは真剣にやりあっている。
が、広告がらみだから原稿料はスンゴク、いい。
スンゴクいいぶん、編集者の注文はスンゴク多い。
そいでもって「障子だ」「襖だ」とアタシたちは口角アワを飛ばしているのである。
つまり藤原定家が、色紙に書いた和歌を「どこに」貼ったかをアタシたちは論じあっているのだ。
アタシは「障子」と書き、それに対して編集者は「襖じゃないか!」と猛り狂っているのである。
古典で「障子」というのは今でいう「襖」のことじゃ。アンタ、高校の古典の授業をさぼったネ!
アタシだって、よほど「襖」にしようかと思った。
が、私が最も信頼する百科事典と信頼できる専門書を調べるとすべてが「障子」になっていたから、
勝手に書き直すわけにもなるまいてと、「障子」のままにしたのじゃ。
そりや、まぁ、
素人さんには不親切ではありましたが。
彼は続ける。
「ぼくが調べた本には襖となってましたが、古典で障子といえば襖のことなんですか」
そうじゃ!
シリーズ3回目のこの仕事だが、彼と組むのは初めてだ。
なかなかフェミニストなオトコであるよと感心したのは打ち合わせのときのうたかたの夢。
仕事に入ると彼は尊大な編集者になった。
曰く。
ぼくが送った資料には、こう書いてあったはずだ、それはどうなった。
ぼくの知っているあの故事を入れろ。
アンタの資料がすべてじゃないョ!
そんなにあれもこれも200字に入れたら「起源」か「歴史」か、わかんなくなるよ!
そう言いたいのはヤマヤマだけど、アタシは単なるライターで、そのうえ原稿料にも不足はないし。
だから、アタシは今日の今日まで可能な限り御意に従ってきた。
そやけど、ねぇ。
なめたら、いかんぜよ。
アタシは「百人一首」を正月の友として育ったんだ。高校時代、アタシは「ミス古典」と呼ばれたりなんかしたんだ。
(言うまでもないが、顔の造作ゆえではない。)
中学の教師になって、研究授業で「平家物語 足摺」を範読したら、眼のカタキだった校長が
「あなたの朗読は素晴らしい。生徒たちも古典の楽しさがよくわかるであろう」
と、このときだけは私をホメたんだ。
ナンカ文句アッカ!
そんなこと、アンタには言わないけどサ。
もうちょっとものの言い方ってもの、
考えたらどうなのさ。
一寸のライターにも五分の魂があるんだそうだからさ。使い捨てライターだからって、
なめたら、いかんぜよ!
電話の相手が心の内でそんな捨てゼリフを吐いているとも知らず、彼は続けた。
「それから、定家の百人一首は、世の中ではもてはやされすぎだと書かれています。それにこれは注文を受けて書いたものでもありますし——」
中世の歌人だって、
霞を食って生きてたわけじゃない。
官位の低かった彼がアルバイトして何が悪い。
注文生産の質が低いと定義するなら、
現在の小説も絵もほとんどアウトだね。
それはまぁ、いい。
アンタが今、言ったことで
ガマンならんことがある。
早口でアタシはまくしたてる。
「もてはやされすぎだとおっしゃいますが、
古今や新古今は技巧に走りすぎる、万葉集の心を歌の心として見なおすべきだ。そういう風潮が明治になってから起こりましたよ。
それは江戸以前の反動としてです。
でも、現在はそういう評価とは別に、やはり定家に対する評価は絶大なものがあるんです。
それとも百人一首はそれほどたいしたものではない、というニュアンスをこの中のどこかに入れるんですか!」
彼は黙った。
あっ、イケナイ!
ここまで言うと、次の仕事が来なくなる。
アタシは吊り上げた目尻をもとに戻し、
頬の筋肉をゆるめる。
仕事の前では、君子じゃなくとも豹変する。
受話器を手にニッコリ笑う。
「スミマセン。私、
ついついむきになってしまって(笑)。
私って気が強いでしょう。
フリーで仕事を続けていると、
どんどん気が強くなってしまうわぁ(笑)。
ほんとにごめんなさい」
これに懲りずに、またどうぞよろしくと、
あからさまには言えない。
マ、言ったようなものだけど——。
彼は毒気を抜かれて
「では、障子のところ襖に変えて、書き直し、
よろしくお願いします」
そう言って電話を切った。
それから何週間かして、
原稿料はいつもどおりでよいかと尋ねると、
彼はどういうわけか原稿料をアップしましょうと言い、さらにつけ加えた。
「いやぁ、この仕事をして、ぼくも勉強になりました。また、どうぞよろしく」
アタシもにこやかに、心から言った。
「ほんとに。私もとても勉強になりました」
(次回に続く)
「嫁の務めは第一に夫の世話、そして子供を立派に育てること」そう主張していた人も、いきいき働く恵子の姿を見て……。Vol.24:「義母が変わった!」は、2024年4月公開予定です。
これまでの話はこちらのサイトで読めます↓↓