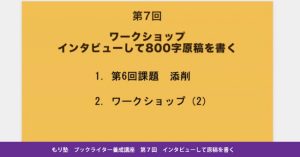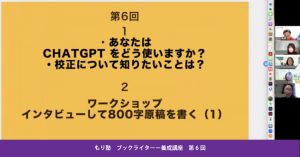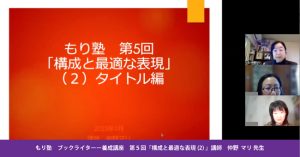専業主婦から出版界で活躍するライター、編集者へ! 森恵子の再就職奮闘記「ハウスワイフはライター志望」第10回。やっと掴んだライターへの道。もっと、もっとライターとして働きたい! でも、そんな恵子を見つめる小さな瞳。仕事か、子育てか ——選べない選択を前にして、葛藤は深まります。
おかあさんとおうちでいたい
二度目の取材予定が入った。私はシンに、そっと尋ねる。
「おかあさん、火曜日にお仕事で出かけるんだけど、誰のおうちで遊ばせてもらおうか?」
シンは言う。
「ぼく……おかあさんとおうちでいたい。ぼくんちでセイジ君と遊びたい。
おかあさんと一緒にいたい」
私の胸がつまる。
つまった固いものがのど元にこみあげて、
私はそれを一気に吐き出す。
止められなかった。
「おかあさんだって……おかあさんだってお仕事したいのよ!
おかあさんだって……ちゃんと生きたいのよ!
やっとお仕事ができたの。おかあさん、続けたい! お仕事がしたいのよ!」
声がつまって、語尾がふるえた。
シンの目の前でぼろぼろ涙をこぼしながら、そう叫んでいた。
シンはじっとそんな私を見ていた。
仕事をやめればいい—— そんなこと、できない!
私は息を整える。
「やっばりお仕事したいの、おかあさん。
毎日じゃないでしょ。ときどきよね。
そのあいだ、お友だちのおうちで遊んでいてほしいな。
シュンちゃんのおばちゃんも、ショウ君のおばちゃんも、セイジ君のおばちゃんも、カズ君やはあちゃんのおばちゃんも、みんなシン君に遊びに来てねって、言ってくれてるよ」
シンはこっくりうなずいた。
それ以後、シンが私の申し出に「いやだ」と言うことはなかった。
4歳は4歳の幼さで、私の心を受け止めたのがわかる。
だから、言ってしまったことに後悔なんかしなければいい—— そう思う。
思いながらうずく。
私はなんてことを子どもに言ってしまったんだろう。
私はなんてわがままな母親なんだろう、とうずく。
それなら仕事をやめればいい——そんなこと、できないクセに。
小さな子を持つ母親が働きに出ることを世間がどう見ていても、
私の心が生き続けるためには必要なのだから。
何がそんなにうれしいんでしょうね
それからしばらくたって、遠いところから声が聞こえた。
「業界誌のライターだって、何がそんなにうれしいんでしょうね」
人づての声を聞いて心が冷えた。
「業界誌」がいけませんか。
どこならいいと言うのですか。
私にとっては教師より業界誌のほうがうれしいのです。
それに華々しくスボットライトを浴びて再就職の道が開けるのは、よほどの才能かバックを持った人だけ。
そんな夢を見られるほど、私は自信家ではないんだもの。
そんな夢を見ているうちに「私の人生は何だったの」という時がすぐにやって来てしまうもの。
それとも、再就職に「ライター」はおこがましいですか。
フツーの主婦の私がめざした再就職が、たまたま横文字職業だっただけ。
横文字職業にあこがれるほど、私はもう若くないもの。
「何がそんなにうれしいんでしょうね」って、あなたの最後の言葉は厳しい。
願ったことが叶えられたとき、喜んではいけませんか。
目障りですか。
「いっつ みい」や「婦人問題講座」で知り合った友人たちが手放しで喜んでくれたから、
シンを遊ばせてくれるおかあさんたちが「がんばってネ」って励ましてくれたから、
同世代の誰もが人の喜びを喜んでくれるような錯覚をしてしまった。
これからは気をつけます。
それからずいぶん日がたち、感情が落ち着くと、彼女に対する気持ちが少し変わった。
彼女もまた、専業主婦だった私があの講座で助言者に感じた、焼けるような思いがあったのかもしれない。
主婦アルバイトのライターにさえそんな羨望を感じてしまうのは彼女のプライドが許さない。
だからあんな言葉になったのかもしれない。
私がそう憶測することさえ、彼女のプライドを傷つける。
彼女もまた、いつか、そうしなければいられないことを見つけるだろうから——。
6月中旬、夫の両親の家にいつものように一泊で行った夜、夫は私が「ちょっとした仕事」を始めたことを言った。
子どもたちがそれぞれに温かい場所で、月4回、面倒を見てもらい、遊はせてもらえることをさりげなく強調して。
「それなら、よかったわね」と義母は言った。
「すんなり話を済ませるためには、おやじとおふくろが揃っているときに、ぼくが言う」
夫の言ったとおりになった。
これで「嫁」が、正々堂々、「ちょっとした仕事」を始める了解がとれた。
私も夫も臆病で、用意周到と狡猾さとでもって、義母の了解をとりつけた。
もっと仕事をしたいけど……
業界誌のそのシリーズは、可もなく不可もなく、1987年9月まで1年半続くことになる。
その期間に私は首都圏のデパート呉服売場をすべて取材した。
デパート大好き人間、きもの大好き人間の私は、楽しんで取材を続けた。
シンはあれ以来、お友だちのおかあさんたちの温かい気持ちに包まれて楽しく遊ばせてもらっていた。
けれども一方で、私はこの楽しい仕事のために、あの人、この人に子どもを預けているという思いがチクチクした。
夫の休日に取材ができたときは、ほっとした。
平日に業界誌の取材日程が決まるたびに、単発の仕事が舞い込むたびに、私はシンの預け先を探した。
シンの希望と希望先の都合、それに私の遠慮がからんだ。
それらは私にいろんなことを考えさせ、さて仕事となったときには残りのエネルギーがもう半分くらいしか残っていない。
そんなふうに思えることもあった。
デパートの取材を始めて半年ほどしたころ、ユミを預かってくれていた友人が転職し毎日の勤務になった。
新しい預け先を探さなければならない。
2歳にならないユミを時間制の保育室に入れることにした。
ベビールームではなく幼稚園に併設されていることが私の安心材料だった。
通わせ始めると違った。
保母がひんぱんに代わった。
迎えに行くと保母のイライラした声が聞こえることが多かった。
いつか映画で見た「さくらんぼ保育園」にはほど遠かった。
ユミは保育室に行くのを、むずかった。
私の迎えにほっとした顔をした。
それほどまでして、続ける仕事だろうか。
私はそれほどまでして、仕事をしたいのだろうか。
何度もそう問う。
あの暮らしには戻りたくない、仕事を続けたい、ほんとうはもっと仕事をしたいと、勇気を出してそのたびに答える。
それならどうして時間制の保育室ではなく毎日ちゃんとした保育園に預けて、きちんと仕事をしないのか、と仕事をしたい私が聞く。
保育室に通うのが毎日じゃないから、ユミは友だちができない。いつもの友だちがいて、いつもの保育者がいて、いつもの遊び場がある。それが子どもにとって一番大事なこと。
そういうことを、あなたは知っているはずだ。
おやつで子どもをなだめながら、母親の帰りを待たせるだけの延長保育がある幼稚園より、5時までが安定した生活になっている保育園。
幼稚園が終わったあと、母親不要のお稽古で子どもの時間をぶっちぎるより断然保育園。
あなたはそう思っている。
保育園が「かわいそうな子どもの通うところ」なんていう認識は、コチコチ頭のおばあちゃまがたや奥様がた、それに子育てを知らない男たちだけの認識にしてもらいたいわね、と時おりあなたは夫に対して口にしている。
それなのにあなたは保育園に子どもを入れない。
どうしてなのかしら。
保育園に預けられない理由は……
お姑さんが干渉しなければ、あなたはとっくに子どもを保育園に預けている。
それはきっとそうだ。
でもほかにも理由があるんじゃないかしら、ともうひとりの私は徹底的にいじわるだ。
子どもが3歳未満でしかも母親がフリーの場合は公立保育園に入りにくいから。
ずっと前シンと連れ立って行った無認可の保育圏は、車で片道30分以上もかかるから。
ユミだけを保育園に入れても状況は変わらないから。
私は言い訳をする。
ホントかな。
あなたが「仕事」をしたかったのは少しの時間「母親」の役割から逃れて、大好きなデパートで大好きなきものを堂々と観賞するためだったような気もしないではないわね。
その上、小さなアクセサリーやバーゲンの洋服が買えるほどのアルバイト代が手に入るなら、一石二鳥ってね。
あなたの生活は、そういう生活だもの。
決して、決して、そうじゃない。
もう少し、待ってほしい。
今は足慣らし。
ゼロでないことだけを大切に、今しばらく暮らさせてほしい。
シンとユミを保育園に通わせても、フリーライターとして仕事が増やせる自信がないから。
それに仕事を始めたときシンの保育園入園を決心せずに、今になって、シンの卒圏まで一年足らずになって、シンの環境を変えてしまうのは勝手が過ぎると思うから——。
仕事らしい仕事がやってきたとき、子どもを保育園に入れられない優柔不断さが、母親にどんな綱渡りをさせるかを、その後私は思い知ることになる。
次回は、本格的ライター稼業と子育ての綱渡りの中、ある事件が……。
Vol.10「録音が……聞こえない!」は、2023年2月中旬公開予定です。
これまでの話はこちらのサイトで読めます↓↓