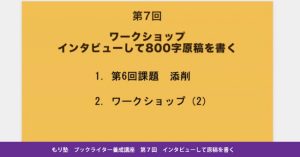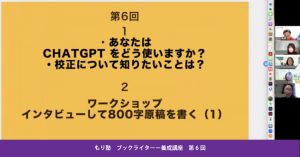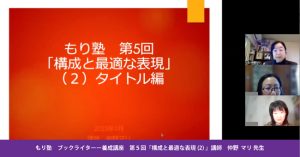専業主婦から出版界で活躍するライター、編集者へ! 森恵子の再就職奮闘記「ハウスワイフはライター志望」第15回。
子供を保育園に預けて、やっと、やっと、ライターとして飛び立てる! その矢先に、夫が言い出したのは……。それでも止まってなんかいられない。いざ、あこがれの編集部へと突進です。
やさしい妻の顔をする
1988年、4月1日。ユミの保育園入園式。
4月6日。シンの小学校入学式。
この日をどんなに待ったことか。子どもたちはそれぞれの集団の中で、やっていくだろう。私があれこれと心配の予測をしても始まらない。4月はあなたたちの門出で、おかあさんの門出でもあるんだから。
そして、もうひとつ門出があった。
夫が念願の博士論文を書き始めたいと言う。
「そろそろ書こうと思うんだ。やるなら休みの土、日しかない。君の取材の日はあける。でも、ほかの休日は協力してほしい」
パートナーの自己実現を喜ぶべきことと思いながら、夫の一方的宣言が気になる。
極論すれば、いつもより大きな論文を書くから子育てには最小限の参加しかできないと言っているように聞こえる。
私は仕事を増やしたいけれど、子育てもなおざりにするつもりはない。なおざりになんかできない。
たとえば保育困の送り迎え、毎日の食事、学校や保育園の参観や父母会。そんな当たり前のことをするのは、いったい誰なのだ。
それに子育ては、そんなルーティンワークだけではない。
手は出さないけれど、何かあったら相談にのるよ。
あなたは子育てをする私のケースワーカーじゃない。私の夫で子どもたちの父親だ。
その論文があなたの生涯設計のひとつであったとしても、ひとりの女の夫とふたりの子どもたちの父親であることも同じくらいかそれ以上に大事なこと。
それくらいわからない人ではないでしょうに。
私は夫にそれを言わない。
彼に協力してあげたいし、何かを言うことで彼の気持ちに水を差すようなことになっては、とやさしい妻の顔をする。
何も言わずに了解の顔をすることが、仕事に出たいと私が言ったとき、「好きなことをして生きるのがいちばん」と私に言った夫へのお礼の気持ちだと思っていた。
それまでに、その後にどんな月日があったのかを私はすっかり忘れたフリをしている。
私の仕事への夫の理解は、かきくどき、訴え、突き付けて勝ちとったものであり、彼への協力態勢は一方的宣言のもとに整えられようとしている。
整えようとする私がいる。
受験勉強中は家の手伝いなんかしなくていいのよ、というような母親には決してなるまいと思っているのに、夫に対してそれをやろうというのだから、私もかなりの馬鹿だ。
私、求人広告、だ~い好き!
4月12日。ユミの慣らし保育も済んだ。
団地の友人にシンの放課後を頼み、都心行きの電車に乗る。
「PR誌以外の仕事もありますから、ぜひ一度、来社してみてください」そう社長自らが言った編集プロダクションヘ。
社長に履歴書と作品を見せた。作品はいつかのショートショートに、あの雑誌の2度目の記事。社長はそれらを気に入った。
「一般雑誌や単行本の仕事も来ますから、そちらのほうを回しましょう」
編集プロダクションのあるビルを出て、深呼吸。
これで一軒!
順風満帆。
出足快調。
至極満足。
私、求人広告って、だ~い好き。
次は某超有名新聞社!
翌日から、また新聞と赤鉛筆の日々が始まる。
ありました。ありました。
某超有名新聞社(!)の都区内フリーペーパー編集部が、ライターを募集している。編集部の所在地は、私が眺めているこの新聞と同じになっている。
かけましょ、電話!
「それでは、19日火曜日の午後1時に」
と女性担当者。
前日は、早寝した。
朝、起きる。
声が出ない!
確かに風邪はひいていたみたいだけど。教師生活で鍛えたはずの声帯がこんな大事な日にこわれないでほしい。大きなハンディになってしまう。
新しい社屋の某超有名新聞社は威風堂々、私の目の前にあった。
屋外からロビー階へすごい高さのエスカレーターがそびえている。私はエスカレーターを見上げながらフラフラと近づく。
ほんとに高い。
新社屋とエスカレーターの堂々ぶりに気後れしてハンディ2。
ロビーに入る。
ピカピカに磨かれた広い床。
あちこちに立つ制服姿は、ガードマンではなく本物の警官らしい。爆破事件の後だからと言ったって、こんな物々しいビルなんて見たことがない。
またハンディが増えるじゃないの。
昼食のためにビル内の喫茶店に入る。
ハンディなんか数えなおすんじゃないの!
ほら、体勢を立て直して!
それともこのビルではライターより物見遊山の人間でいたいってわけ?
そう叱咤激励しながら、サンドイッチをほおばる。
12時55分。私は席を立つ。
編集部は思ったより小さかった。
数人分の机があるだけだ。
これなら私でも大丈夫かもしれない。
電話の際の女性が出てきた。
責任者だと彼女は言った。
初対面のあいさつより前に、風邪をひいて今朝、突然声がでなくなったことを、詫びなければならなかった。
「大丈夫です。履歴書と作品を拝見できれば」
今度の作品は、先月号のミニコミ紙にした。
印字ミスはあったが、エッセイストの鶴田静さんをインタビューした記事は友人たちに好評だった。
声の出ない面接で間の抜けた時間が過ぎ、最後に彼女が言った。
「お風邪のところ、大変でしたでしょう。今日の結果は、後日連絡いたします」
その夜、採用の確率は半々だと思った。
次の日には、4割になった。
そのときは聞き流してしまった彼女の言葉が、次々と気になる。
「うちは都区内だけに発行している情報誌なんです」都区内のロコミ情報に詳しい人を欲しがっていたみたいだ。
「よく、風邪をおひきになるんですか」
風邪がちのフリーランスなんて、どこだって敬遠する。いつもはほとんど、なんて言っても目の前でひいてるんだから信用ならない。
都下郊外のミニコミ紙を持ってきた風邪ひきライターに対する彼女のもの柔らかさは、私に対する好感度じゃなく、業務用にすぎなかったような気がする。
そう思い始めると、確率の数字はシュルシュルしぼんでいった。
しぼみながら、電話のベルが嗚るたびに、私は期待と不安の反応をした。
1週間近くたって、採用の確率予想が私の中で1割未満になったころ、また電話が嗚った。
受話器から声が流れるその瞬間に、仕事の電話だ、と思った。
期待した女性の声ではなく、あの編集プロダクションの社長の声がした。仕事の依頼だ。
飢えた魚が工サに飛び付くような声じゃ、足元を見られてしまう。かといって、とりすましすぎて、相手を当惑させるような声は今後のためによろしくない。
営業上、これからの私に必要なのは中庸的態度、つまり落ち着きという自信表明の態度なんだから。
つつがなく受話器を置いた。
飢えた魚は、ひさしぶりのエサを味わう。
ゴックンとそれを飲み込んで、もう新聞社からの電話を待つのはやめようと決心した。
「編集長はいらっしゃいますか」
でも、もうひとつくらい違った味を味わってみたい。
きもの雑誌の編集部に電話してみようよ。
それは独身時代、母が購読し、私が定期的に見たたったひとつの雑誌。求人広告をだしているわけでもないその雑誌に電話をするのは、新しく仕事が舞い込んだ今をおいてほかにない。
それに1、2年前、読者の欄に私の投稿が載ったこともあるんだし。私はホントの愛読者だったんだし——。
とうとう編集部のダイヤルを回した。
そして大胆なフレーズを言う。
「編集長はいらっしゃいますか」
私、ほんとは「長」と名のつく人は苦手。
「校長ぎらい」の教師生活の後遺症だっていうことくらいはわかっている。
原因はわかっていても苦手は苦手。
それでもやる気になれば、何だってやっちゃうのね、あなた。
強くなったね、あなた。
受話器から流れるメロディーを聞きながら、私はそう自画自賛した。
自分自身への励ましとして。
メロディーがとぎれた。
「代わりました。編集長の××ですが」
編集長の電話口で男性の声がした。
自己紹介に続けて、
「雑誌をいつも拝見させていただいております。実はそちらさまで、お使いいただけないかと思いまして——」
電話の向こうで、ほんの少し沈黙。
紹介者もなく、いきなりこんな電話をする人は、珍しいのだろうか。珍しくったって何だって、したい仕事先にコネがなければ、自分で売り込むほかないじゃないの。
コネなし、カオなし、業界事情に疎い主婦ライターは、開き直る。
「うちは外注ライターを一切使わない方針なんですが、今まではやはり、きものの関係のお仕事をしていらっしゃったんですか」
「はい、半年くらい前まで、フリーで業界誌の記者をしておりました」そう答えると編集長の声が少し変わった。
「何という雑誌ですか」
あの業界誌の名を告げた。
「そうですか。そこでどんな記事を」
あの業界誌の記事が、私のキャリアになるとは思えない。有名出版社の編集長が私の記事を知っているとも思えない。
でも答えるしかない。
デパート呉服部のシリーズ記事です、と。
「ああ、読んだような記憶がありますよ」
冷や汗が噴き出す。
あれはひどい。
あれはまずい。
今ならもう少しマシな記事が書けると思います。
そんなことは言えない。
編集長は気持ちを動かされたらしい。
「では、一度お目にかかりましょうか」
編集長は3日後を指定した。
あこがれのきもの雑誌の編集部に乗り込んで、編集長と対等に語り合って……。でも心の奥にはむず痒い「女性編集者アレルギー」が……。
Vol.16「勤めてみる気はありませんか」は、2023年7月下旬公開予定です。
これまでの話はこちらのサイトで読めます↓↓