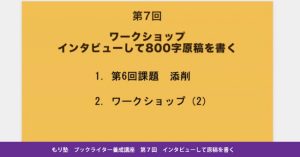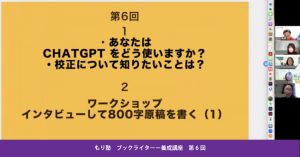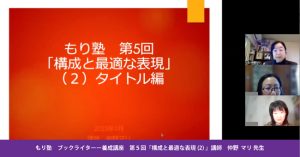専業主婦から出版界で活躍するライター、編集者へ! 森恵子の再就職奮闘記「ハウスワイフはライター志望」第8回。
辞書編纂のアルバイトを終えて、『WIFE』にも投稿して、資格試験も受けて。でも本当は「ライターになりたい」! その言葉が口にできない自分に苛立つ。そんな時かかってきた一本の電話は……。
ホンネとタテマエの間で
年末年始を夫の実家で過ごした。
1986年の年明け早々、夫は「資格試験特集」を組んだ雑誌を買ってきた。
夫は彼の両親の前で行政書士試験に受かれば次にチャレンジする資格を考えてみたら、と言う。
「税理士なんか、いいんじゃないか」と夫が言えば、舅は「1科目ずつ受けられるから長期計画でやれば、そうむずかしくはないよ」と続ける。
舅にとって「試験勉強をする母親の姿は子どもの教育上望ましい姿」だった。あるいは、その言葉を姑にむけて言ったのかもしれない。
夫と舅。
ふたりの男たちが、仕事をしたい私と、仕事などとんでもない姑の間にいて、「資格試験」で私と姑の間をつないでいた。
1月中旬、行政書士試験の合格通知が来た。
すぐに『WIFE』に投稿するために合格体験記を書いた。
「次は税理士に挑戦してみようかな」と私は自分をねじ伏せるように書き、最後の最後に本音のつぶやきが漏れた。
「本当のことを言えば、文章を書いて何がしかのお金を得られれば、私にとってこれ以上の幸せはないんだけど……」
本当に本当のことを言えば、私の気持ちは「……」がつくようなものじゃなかった。本音の雑誌『WIFE』にも、私はつぶやきの形でしか本音を書けなかった。
私は自信がなかった。
わけても文字にして、真っ正面から編集部に仕事の意志を伝えることに。
学生時代、男の子たちと対等にわたりあってきた私はもうどこにもいない。
「おまえ、カミソリみたいに物言うなぁ」
そんな私はもうどこにもいない。
小学校時代から16年も持ち続けたその美徳は、たった4年の教師生活であっさり消えて、ホンネとタテマエを使い分ける私ができた。
「家」意識が残る結婚や社宅暮らしが使い分けに磨きをかけ、ホンネを言うときにさえつぶやきになる私がいる。
「いっつ みぃ」や「婦人問題講座」は、そんな私にわずかに開いた小さなホンネの社会だった。
幸運の女神様、降臨!
2月、4回めのその雑誌を手にした。
私の投稿がやはり載っていた。
しかし、それだけだ。
編集部に私の意志をアピールしたい。
だから合評会に出席しよう。
その日は平日。あいにくの雨。
1歳を過ぎた娘を背負って会場に出向いた。
「私、ライターになりたいんです」
そんな気持ちを、合評会に行くことで示したつもりだった。
言葉にしなきゃあ、わからないのに。
合評会が終わって、娘を背負おうとすると、編集長と副編集長が私の背に娘をおぶわせてくれた。
「雨の中、こんなに小さいお子さんを連れて大変だったでしょう。ご苦労さま」
私の背中も物が言えるといいのに。
私は煮詰まっていた。
3月が巡ってきた。初めて友人たちに「原稿を書く仕事をしたい」とつぶやいてから、2年。『WIFE』という雑誌の存在を新聞記事で知ってからちょうど1年がたった。
夜、電話が鳴った。
「わいふ編集部の和田です」
とその声が言った。
辞書のアルバイトのとき、合評会のとき会った副編集長の声。
私が心の底で待ち望んでいた声。
私は受話器を握りしめた。
「あなたに頼みたい仕事があるんですがね」その声は続けた。
私は受話器をさらに強く握りしめ、
「はい」
とうわずった返事をした。
「きものの業界誌の仕事なんですが」
私の幸運の女神様は男のようなきびきびとした口調だった。
「きものにくわしいライターをさがしているところがあってね。あなた、いつか書いてたでしょう。日舞という特技も結婚後は生かすところがないって。それが印象に残っていてね。編集長とも相談して、あなたならきものに詳しそうだってことになったんだが。お子さんが小さいから、大変かもしれないが、やってみる気はないかな」
やります、やりますとも。
「はい、ぜひやってみたいです」
この期に及んで、私にできるでしょうか、などと謙譲の美徳を発揮するほど、私も愚かではなかった。
それが幸いした。
後で知ったのだが、この女神様はとても気が短いのだ。
幸運の女神様らしく後ろ髪がないのだ。
「じゃあ、とにかくご主人にもよく相談して」
そう言って、電話が切れた。
受話器を握りしめた手が汗びっしょりになっていた。受話器を置く。幸運にうっとりする。
〽さても源の牛若丸今宵も五条の橋に出でェ
そんな曲が私の耳元で聞こえる。
舞台の袖で、私は桜色の被衣を深くかぶり、浅葱色の大口袴をはき、稚児まげの鬘をかぶり、横笛を手にしている。
すり足でゆっくり舞台へ進む。
劇場の拍手に迎えられる。
被衣をかざして下手むこうを見る。
劇場が静まる。私は笛を吹く。
お師匠さんの弁慶が登場する。
私は弁慶と対峙し、弁慶が私の足を払う。
私はたたらを踏み下手前へ。
拍手が大きな波になる。
やがて大詰めがやってきて、牛若丸が刀をかざし、弁慶が長刀を持って決まる。
チョンと柝が入る。
私と師匠の息はぴったり合っている。
下手むこうと上手むこうを互いに眺める視線が交わる空間に結ぶものは平安末期の武勇か、江戸の絢爛か。
不埒な私はずっとずっと向こうを見ている。
教師生活で押し殺している私の息が吹き返す、その姿を私は見ている。
楽屋で化粧を落とし、風呂を浴び、紋付に着替える。幕間に観客席に入ると、私の周りがざわめく。
「ホラ、あの人、さっきの」
小さなささやきが聞こえる。
私はこの瞬問も好きだった。
それが私の日舞の風景。
そんな風景を愛惜を込めて振り返ること、「私は日舞を捨てたのに、あなたは何ひとつ変わらない生活をしている。こんな結婚形態はとても不公平」と夫に不満を言いながら暮らすこと。
今、私はそんな暮らしを少しずつ変えようとしている——あの投稿には、確かそんなことを書いたはずだ。
長いうっとりのあと、電話の最後の言葉を思いだす。
「ご主人にもよく相談して」
それは大丈夫。
私の「ご主人」は準備万端整えて、妻の出番を待っているはずだ。
◆いざ出陣、ライターデビュー!
副編集長からの仕事の依頼を伝えたとき、夫は予想どおり「いいよ」と言った。
「できるだけ、ぼくが休みの日にすればいい、取材の日を。そうすれば、子どもたちを見られるから」
予想以上の反応だった。
私のモンモンの2年間は無駄ではなかった。
その出版社に副編集長とふたりで行くことになった。
夫に伝えた。
「その日は、ちょっと休むのは無理だなぁ」
私は驚いた。
夫がそう言うとは思ってもいなかったから。
「あら、そんなこと、いいのよ。母に来てもらうから」
私はやってきた仕事に有頂天で、この絶好のチャンスを逃がした。
夫も私も仕事をし、夫とふたりで子育てをし家事をする。
お互いひとりでも生きられるけれど、お互いの選択で家族として生きる。
そんな私の理想の家庭を実現する最初の一歩を。
このひとことが、私のモンモンの2年間の1年くらいをふいにした。
実家の母が上京した。紺色のシンプルなワンピースを携えて。
ワンピースは、今の私から見ればPTA用ウエアに毛がはえたものにすぎなかったが、そのときの私の目には仕事着らしく映った。
母の手を借り、母の選んだワンピースを着ながら、本人は「女の自立」の第一歩と勇んで、その洋服に似合いの主婦のアルバイト先に面接を受けにでかけた。
私のあふれる喜びはやってきた仕事を「主婦のアルバイト」などと思えるはずもなく、「とうとうアコガレのライターになれるんだ」と騒いでる。踊ってる。歌ってる。
日本橋にあるその出版社はガランとしていた。
大部分のデスクは記者がでかけた後のものではなく、見離されたデスクだということは、素人の私の目にもぼんやりとわかった。
そんなこと、かまわない。
私ははりきって面接に臨む。
初老の社長とわいふ副編集長と私。
1時間ばかり話した。
結果は後日とのことだったが、副編集長も私も多分、大丈夫だと思った。
私は金縁メガネではなかったし、ニコニコしながらさりげなく私が「きもの通」だということをアピールしたし。
予想どおり、2、3日たって合格の返事が来た。4月から、首都圏のデパートの呉服売り場を取材することになった。
次回は、いよいよライターデビュー、でもその前に立ちはだかる高い壁……。
Vol.9「遠くの姑、近くの友人」は、2022年12月中旬公開予定です。
これまでの話はこちらのサイトで読めます↓↓